70歳の誕生日を「古希」といいます。中国唐代の詩人・杜甫の「人生七十古来稀なり」という詩句に由来する言葉です。つまり、杜甫の時代は、70歳まで生きられる方は、そう多くなかったのです。
杜甫の時代から1300年を経た現在、人生100年時代と呼ばれるようになりました。40歳、50歳は若造扱いで70歳といえども第一線で働いているケースも珍しくありません。
しかし、気になるのは経済面です。定年後の契約更新で給与が半減したり、若い方に道を譲ってリタイアしたりした方も少なくないでしょう。
ここでは、70歳からの投資・資産運用は可能かを検証し、具体的な方法と注意点を解説します。本記事が、70歳からの豊かな人生のための一助となれば幸いです。
70歳になっても投資や資産運用はできる?
70歳を迎えると、多くの方が「もう投資や資産運用を始めるには遅いのでは?」と感じるかもしれません。しかし、結論から言えば、70歳になっても投資や資産運用を行うことは可能です。むしろ、豊富な人生経験に基づいた適切な計画とリスク管理を行えば、シニア世代にとっても有益な選択肢となり得ます。
なぜ70歳でも投資が可能なのか?

70歳の誕生日を迎えられて、終活を始める方もいるかも知れません。しかし、意外とそれは古来から刷り込まれてきた70歳 = 老人の固定観念であり、実はまだまだ体力も気力も旺盛な方が大勢いらっしゃいます。
元気であれば、やれること・やりたいことをやるのが人生です。
ここでは、70歳からの投資が可能である理由について、3つの観点から解説します。
ライフステージに応じた目標設定
70歳といえども、これからの人生にはまだ多くの時間があります。平均寿命が延びている現代では、80代、90代まで健康に過ごす方も珍しくありません。そのため、資産をただ貯めておくだけでなく、適切に運用して増やすことで、将来の生活の質を向上させることができます。
多様な投資商品の選択肢
投資と聞くと株式やFXなどリスクの高いものを連想しがちですが、70歳からでも始めやすい選択肢はたくさんあります。例えば、債券や投資信託、定期預金など、比較的リスクの低い商品を選ぶことが可能です。また、不動産投資信託(REIT)なども安定した収益を見込める選択肢として人気です。
インフレ対策
老後資金として貯蓄してきた現金をそのまま持っているだけでは、インフレによってお金の価値が目減りしてしまう可能性があります。投資を通じて資産を増やすことで、このリスクに備えることができます。
70歳からの投資・資産運用で 注意すべきポイント
70歳からの投資・資産運用は、注意すべきポイントが若いうちより増えるのは確かです。実際、高齢になってから投資詐欺の被害に遭われた方のニュースが報じられることが多々あります。
ここでは、70歳からの投資・資産運用で 注意すべきポイントについて解説します。
リスク管理
年齢を重ねるほど、鈍感になり、リスク許容度は低くなります。そのため、大きなリスクを取る投資は避け、安全性が高い運用方法に焦点を当てるのが賢明です。
短期的な視点で計画を立てる
資産運用の期間としては、比較的短めの方が賢明といえます。例えば、5年後や10年後に必要な資金を考慮しながら計画を立てることが大切です。
ただし、次世代へ引き継ぐ前提だったり、投資商品の性質においては長期的な視点での計画も有効です。70歳の20年後の90歳でこそ、資金が必要になる場合もあるからです。
専門家のアドバイスを活用する
金融商品やマーケットの知識に自信がない場合は、ファイナンシャルプランナーやライフプランナー、証券会社のアドバイザーに相談するのが望ましいでしょう。自分に合ったプランを提案してもらうことで、安心して運用を始めることができます。
70歳からでもできる投資・資産運用5選|方法と注意点

70歳を迎えたからといって、資産運用を諦める必要はありません。むしろ、適切な運用方法を選べば、安心した老後を過ごすための強力なサポートとなります。しかし、リスクを最小限に抑えつつ、無理のない計画を立てることが重要です。
ここでは、70歳でも始められる投資・資産運用方法を5つ紹介し、それぞれの注意点を解説します。
定期預金
銀行や信用金庫で提供される定期預金は、元本保証があり、リスクが少ないのが特徴です。一定期間預け入れることで、普通預金よりも高い金利を得ることができます。
ただし、金利が低いため、大きな利益を期待することは難しいでしょう。また、途中解約するとペナルティが発生することもあります。したがって、預ける資金を使う予定がないか確認してから始めましょう。
国債(個人向け国債)
日本政府が発行する国債は、安全性が高く、特に「変動10年型」などはインフレにも対応するため、安定した運用が可能です。
満期まで保有することが基本となるため、中途解約時の条件を確認しておく必要があります。また、利率は低いため、、他の運用方法と組み合わせることも視野に入れておきましょう。
株式投資(配当株中心)
配当利回りの高い株式に投資することで、安定した配当収入を得られる可能性があります。特に日本株の中には、配当実績が安定している企業も多く存在します。
株価の変動リスクがあるため、資金の一部だけを投資に回すことをおすすめします。また、業績悪化により配当が減少するリスクもあるため、企業の情報収集を怠らないようにしましょう。
急騰株に強いこちらのサイトなど、ぜひ参考にしてみてください。
成長株を見つけたいなら【ウルフ村田式 株式トレード体験セミナー】![]()
『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!![]()
投資信託(低リスク型)
複数の資産に分散投資している投資信託は、初心者にも取り組みやすい選択肢です。特に債券型やバランス型の投資信託はリスクが低く、高齢者にも適しています。
信託報酬(手数料)がかかるため、費用対効果をしっかり確認しましょう。また、元本保証ではないため、リスク許容度を考慮して選ぶ必要があります。
不動産投資(小口化商品)
REIT(不動産投資信託)やクラウドファンディング型の不動産投資は、小額から始められ、不動産収益を分配金として受け取ることができます。
不動産市況の変動や運用会社の経営リスクに注意が必要です。また、流動性が低い場合もあるため、急な現金化には不向きです。
不動産投資についてはこちらの記事でも案内しています。
下記サイト共々、ご参照いただけると幸いです。
始める方が増えている不動産投資!始める前の無料相談は【トウシェル】で!![]()
1万円からはじめる不動産投資 FUNDROP
自分を知り尽くした70歳だからこそやれることは多い
70歳という年齢は、新しいことに挑戦するのに遅すぎるということはありません。投資や資産運用もその一つです。ただし、自分のライフスタイルや目標に合った方法で無理なく進めることが大切です。
「安全性」と「流動性」を重視し、大きな利益を狙うよりも、安定した収益を目指しましょう。無理のない範囲で計画的に取り組み、自分自身の生活スタイルや目標に合っていれば、それに越したことはありません。必要に応じてセミナーを受講したり専門家に相談したりしましょう。

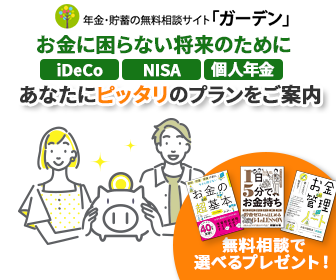






コメント