NISAとは、購入した金融商品による利益が非課税になる制度です。
そして2024年1月から始まったのが新NISA、従来のNISAの非課税枠を大幅に拡充し「つみたてNISA」と「一般NISA」を統合して利用しやすくしています。。
非課税期間が無期限となったため、運用期間が長ければ長いほど得をすることになります。若い投資家の利用が多いのはそのためでしょう。一方で、年齢的なことを理由に新NISAの利用をためらっている方もいるのではないでしょうか?
本記事では「新NISA」について幅広い年代の方に向けてわかりやすく解説します。どのタイミングで始めるべきか、そして口座開設の手順と賢い運用方法についても詳しく紹介します。
本記事を読めば、どの年代の方でも、新NISAに対して今より前向きになれるでしょう。これから資産運用を始めたいと思っている方、新NISAを検討中の方はぜひ参考にしてください。
新NISAと旧NISAの違い
改めて説明させて戴きますが、NISAとは投資・資産運用の利益が非課税になる制度です。通常の投資や資産運用においてはある一定額以上は課税されますが、NISA口座からの運用なら課税されません。新NISAは、その旧NISAの非課税額が大幅に拡大し、しかも非課税期間が無期限という、とんでもなくお得な制度です。
以下は旧NISAと新NISAの比較表です。
| 新NISA | 旧NISA | ||
| 一般NISA | つみたてNISA | ||
| 最大利用可能額 | 1,800万円 | 600万円 | 800万円 |
| 年間投資の上限 | 360万円(120+240) | 120万円 | 40万円 |
| 非課税期間 | 無期限 | 5年間 | 20年間 |
| 実施期限 | 2024年~(無期限) | ~2023年 | ~2042年 |
最大利用可能額の大幅拡充と売却後の再利用
比較表で一目瞭然の通り、最大利用可能額が桁違いになっています。しかも旧NISAでは保有している商品を売却しても非課税枠が復活することはありませんでしたが、新NISAでは非課税枠が復活し、再利用が可能です。売却した分の枠が翌年に復活するため、同じ枠を再利用しながら長期にわたり売買を繰り返すことができます。したがって、累計の投資額が1,800万円を超えても新NISAを利用することが可能になりました。
年間非課税枠の拡大
新NISAでは年間投資額の上限が360万円(成長投資枠120万円+つみたて投資枠240万円)となりました。旧NISAではつみたてNISAが年間40万円、一般NISAが年間120万円でしたが、新NISAでは、つみたて投資枠で年間120万円、成長投資枠で年間240万円まで上限が引き上げられました。
しかも、旧NISAではどちらか一方しか選択できませんでしたが、2024年スタートの新NISAからは併用が可能になり、年間360万円まで投資できるようになっています。
一生涯にわたって非課税
旧NISAの「20年」や「5年」という期限がなくなり、新NISA口座で購入した資産はずっと非課税で運用できます。この無期限非課税により、年齢や収入を気にせず、誰でも気軽に利用できるようになりました。もちろん60歳でも70歳でも80歳でも可能です。
新NISAを始めるのに適した年齢は?

「新NISAを始めるのに適した年齢は?」という質問をよく耳にしますが、結論から言うと「早ければ早いほどよい」です。なぜなら、資産運用は時間を味方につけることが非常に重要だからです。
新NISAによる資産運用は、18歳以上なら何歳でも可能であり、年齢層によって運用のポイントが異なります。以下に世代別のポイントを解説します。
【 20代・30代の新NISA】時間を最大限に活用
20代や30代は、運用期間を長く取れるため、「複利」の効果を最大限に活かせます。例えば、月々2万円を年利5%で30年間運用した場合、単純計算で元本720万円が約1,600万円となります。若いうちの少額での投資が、長い時間の複利効果で将来の大きなリターンとなり、資産形成に余裕が生まれます。
【40代・50代の新NISA】老後資金の準備として有難い無期限非課税
40代や50代でも、新NISAは十分に活用できます。この年代では、子どもの教育費や住宅ローン返済などで出費が多い時期かもしれませんが、逆に収入も安定しているので投資計画を立てやすい時期です。
少額からでも投資を始めることで老後資金の準備ができます。新NISAの非課税無期限化によって、焦りやプレッシャーを感じることもありません。加えて、社会の酸いも甘いも知り尽くした年代ゆえの情報収集力や手腕でいっそう効率的な運用も視野に入ってきます。
ただし、そうした冒険心につけこまれて投資詐欺に遭ったという方が多いので十分注意すべきでしょう。定年退職後の具体的な目標を設定し、慎重に運用しましょう。
【 60代以上の新NISA】退職金や余裕資金の活用でリスク最小限に!
60代以上の場合、新NISAを活用する際にはリスクを抑えた運用がポイントです。株式中心のポートフォリオではなく、安定した債券やバランス型ファンドを選ぶと、ことで、元本割れのリスクを軽減しつつ比較的安定した運用が可能です。
退職金や預貯金の余剰金など、リスクの少ない中での資産運用を心掛けることで、精神的にも安定し、老後の生活費や趣味の資金を増やすことができます。新NISAの非課税無期限は、高齢者にとって大きな恩恵となっています。
新NISA口座の開設方法

新NISAを始めるにはまず口座を開設する必要があります。手続き自体は簡単ですが、いくつか注意点がありますので順を追って説明します。
1.金融機関を選ぶ
新NISA口座は、証券会社や銀行などで開設できます。選ぶ際には以下のポイントをチェックしましょう。
- 取引手数料や管理費用はどうか?。
- 自分が投資したい商品を扱っているか?
- 初心者向けのサポート体制が整い最新情報が充実しているか?
ネット証券は手数料が安く初心者にも使いやすいので人気です。投資初心者の未成年から年配の方まで幅広い年齢層に利用されているネット証券といえば
松井証券が有名です。老舗として抜群の信頼があり、株主優待生活でおなじみの桐谷さんも利用しています。また、世界中の投資家がダウンロードしている投資アプリが【ウィブル証券】
こちらも高い実績を誇ります。
一方、対面でないと不安だという方もいらっしゃいます。そうした方には、下記のようなWebセミナーや相談窓口があります。お近くの会場で実際に講演会やセミナーを開催することも多いので、ぜひ問い合わせてみてください。
スマホで参加!無料の資産運用セミナーで投資を学ぼう【マネきゃん/Money Camp】
賢いお金の増やし方入門セミナー
お金の悩みを解決するWeb相談、特典あり!
LINEで相談しながら資産形成
2.必要書類を準備
新NISAの口座開設には以下の書類が必要です。
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
オンラインで手続きをする場合は、上記書類を撮影してアップロードすればOKです。
3.申し込みと審査
金融機関のウェブサイトから申し込みを行います。その後、審査が行われ、数日〜数週間で口座開設完了の報せが届きます。完了通知が届き次第、すぐに投資を始められます。
新NISAの賢い運用方法とは?

新NISAで成功するためには「計画的な運用」が大切です。「計画的な運用」の鍵となるのが以下の3つです。
- 長期・分散・積立
- リスク許容度の把握
- 定期的な見直し
それぞれの具体的なコツについて解説します。
長期・分散・積立
新NISAでは、「長期・分散・積立」の3つの基本原則を守ることが重要です。
すなわち、時間を味方につけてリスクを分散し(長期)、複数の商品や地域に投資してリスクヘッジ(分散)します。さらに、定期的に一定額を投資することで、市場の上下動に影響されにくくなるでしょう(積立)。
特に、つみたて投資枠では、インデックス型の投資信託が有効です。手数料が低く、安定した成長が期待できます。
2.リスク許容度の把握
投資はリターンだけでなくリスクも伴います。自分がどれくらいのリスクを許容できるかを考え、それに応じた商品選びをしましょう。運用期間が短ければ短いほど、慎重さが求められます。
たとえば「リスクをできるだけ抑えたい」という方には債券型の投資信託などが適しているでしょう。また「リターン重視で攻めたい」という方には株式型の商品が向いています。
3.定期的な見直し
投資環境や自分のライフステージの変化に応じて、ポートフォリオ(投資商品の組み合わせ)を見直すことも大切です。たとえば、結婚や出産などの大きなライフイベントの出費に合わせた運用や、年代ごとの収入に応じた投資額の変更など細やかな見直しも必要になってきます。
ご自身だけの考えで不安な場合、躊躇なく専門家や金融機関に相談しましょう。
まとめ
新NISAは、幅広い世代にとって魅力的な制度です。その最大のメリットである「非課税」をフル活用するためにも、早めにスタートし、計画的に運用することが重要です。この場合の早めとは年齢的なことはもちろん、気付いた時点という意味を含みます。
非課税無期限という制度は、多くの人にとって大きな希望です。それぞれのライフステージに合った方法で賢く運用し、ぜひ有意義な人生にお役立てください。
本記事が、みなさまの豊かな未来への一助となれば幸いです。

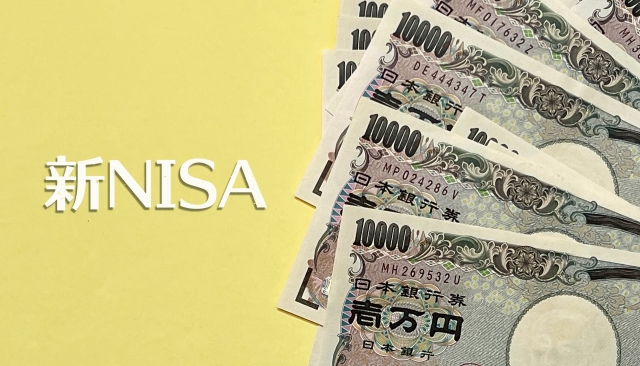




コメント