プラチナNISAは、現在のNISA制度が主に若年層の長期積立投資を前提としているのに対し、高齢者の資産活用ニーズに応えるために提案されています。金融庁は2026年度の税制改正要望にこの制度を含める方向で検討しており、元首相の増税メガネこと岸田文雄氏や自民党の資産運用立国議員連盟が推進しています。
あの人の言うことだから信用できない、と思われるのは仕方ありません。しかし、あの人とあの党なら、選挙対策を兼ねて自身らの中抜けを前提としたさまざまな特典を付けてくるという考え方もあります。
感染症対策で散々振り回されて我々国民は賢くなりました。今回のプラチナNISAに関しては、メリット・デメリットを踏まえたうえで得るべきものは得、一円も無駄にしないようにしましょう。
2025年5月時点でのプラチナNISAに関する情報を集めました。ご参照ください。
プラチナNISAの概要
プラチナNISAは、日本の高齢者(特に65歳以上)を対象とした少額投資非課税制度(NISA)の新しい形態として金融庁が導入を検討中であり、2026年度の税制改正要望に盛り込まれる予定です。この制度では、「毎月分配型」の投資信託を利用でき、運用益を毎月分配金として受け取ることができます。これにより、高齢者が資産を計画的に活用し、生活費を補填することが期待されています。
プラチナNISAのメリットの詳細
生活費の補填: 特に年金だけでは生活が厳しい高齢者にとって、毎月の分配金は重要なキャッシュフローを提供します。楽天証券の分析では、まとまった金融資産を持つが年金で賄えない場合、毎月分配型投信が生活費を補う手段として合理的な選択肢とされています(楽天証券)。
資産管理の柔軟性: 高齢者が資産を段階的に引き出し、計画的に活用できる点が評価されています。これは、長期的な資産形成よりも短期的な現金ニーズに応える設計です。
プラチナNISAのデメリットとリスク
毎月分配型の投資信託は、高い分配率を維持するためにリスクの高い運用を行う場合が多く、元本が減少する可能性があります。楽天証券の分析では、多くのファンドの純資産価値が10,000円から3,000〜6,000円に下落している例が指摘されています。
販売手数料や信託報酬が高いため、投資家の実質的なリターンを圧迫する可能性があるからです。 分配金の一部が元本の返済である場合、投資家が利益と誤解するリスクが生じ、特に高齢者にとっては理解しにくいと指摘されています。
プラチナNISAの特徴
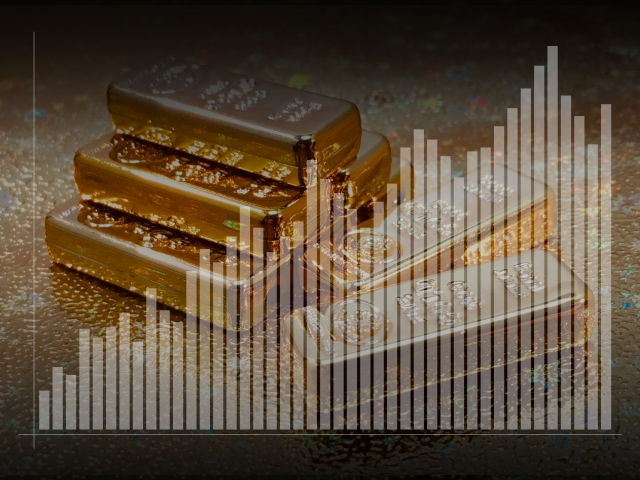
プラチナNISAの主な特徴は、運用益を毎月分配金として受け取る「毎月分配型」の投資信託を対象に含む点です。例えば、元本10万円でスタートし、運用が順調なら利益の一部が毎月分配されますが、運用が低迷した場合、元本の一部が取り崩される可能性があります。この仕組みは、資産を計画的に活用し、毎月の生活費に充てることを目的としています。
毎月分配型投資信託の注意点
毎月分配型投資信託は、運用をしながら一定額を収益分配金として取り崩せる投資信託です。元本はもともとご自分のお金ですから受け取って当然であり、毎月一定額が分配されることは安心につながります。
事実、かつて元本取り崩しサービスがなかった頃には「運用しつつ、取り崩しもしていきたい」ニーズに応えられる商品として一大ブームとなりました。しかし今は、投資信託を部分的に解約して取り崩すことは楽天証券の「定期売却サービス」やSBI証券の投資信託定期売却サービスなど、容易になっています。
したがって、運用手数料の高い毎月分配型投資信託を、非課税口座のNISAで購入するだけのことです。
「取り崩しできるので、高齢者の方も毎月安心して生活できますよ」と言いたいのかもしれません。
元本払戻金と信託報酬で目減りする可能性
分配金を貰ったからといって、儲かっているとは限りません。分配金を出す投資信託は、利益が出ていないときでも無理に元本払戻金(特別分配金)として、投資した元本の切り崩しを行います。
たとえば100万円投資して10万円の元本払戻金をもらった場合、元本は90万に目減りし、さらに信託報酬という手数料も引かれてしまいます。すなわち、銀行預金と同じように、投資元本を手数料を払いながら返してもらう可能性も否定できないのです。
高齢者がプラチナNISAを活用する際のポイント

高齢者の投資・資産運用には、若い方にはないリスクが伴います。それは判断力の衰え、認知機能の退化、そして病気やケガがなかなか治りにくくなり生命の危険な状態になる可能性が高くなります。
そうした毎日だからこそ、投資・資産運用でうまく生活していきたい、という方もいるかも知れません。以下のような対策を講じておくと安心でしょう。
- 家族信託:家族に委ねる方法
- 任意後見制度支援信託:本人の生活文を差し引いて金融機関に委ねる
- 出口戦略を決めておく:何歳までとか、手を出さない投資とかを決めておく
プラチナNISAの特典|日本株長期保有で「相続税免除」も?
提言によると、プラチナNISAに対して「相続税の一部免除」を検討しているとのことです。
その根拠は、高齢者の保有する資産はそのまま子孫への「相続資産」となるケースがほとんどだからです。岸田さんらには、その「相続資産」の活用によって、経済を活性化したいとの狙いがあります。それが「プラチナNISA」案であり、ならば「相続税減免」の特典をつければ需要が高まるとの考えでしょう。
「相続資産」の経済循環で停滞する日本経済の活性化?
そもそも日本経済が停滞したのは、国内被災地を看過しての海外支援と度重なる増税に原因があったのではないでしょうか?
岸田政権といえば、こっそりブルガリアに自衛隊を派遣していたり、ウクライナ支援のキックバックを受け取ったり、やりたい放題の戦後最低政権だったと記憶しています。
ただ、比較的余裕のある高齢者にとっては、相続税減免のメリットは大きいでしょう。高齢者が、というよりは高齢者の保有する資産が経済循環を促し、日本経済の活性化につながればそれに越したことはありません。
プラチナNISAの賛否と議論

プラチナNISAには賛否両論あります。一方で、証券業界や銀行はシニア層の投資マネーを取り込むチャンスと見ていますが、高齢者からは「リスクを背負いたくない」「手数料が高い」といった懸念の声も上がっています。また、参議院選挙対策や金融業界への配慮との見方も一部で指摘されています
岸田氏は面会後の取材に、「『子ども支援NISA』とか『プラチナNISA』という形で全世代型に拡大していく」と語っています。大多数の国民に支持されなかった総理ということは念頭に置いておきましょう。
ちなみに2チャンネル創設者の「ひろゆき」氏ですら「生活保護を取りやすくするとか進めた方が絶対的貧困世帯は助かると思うんだけど」と批判的な意見を述べています。
まとめと今後の展望
プラチナNISAは、高齢者の資産活用ニーズに応える重要な制度として提案されていますが、リスクやコストの問題が議論の焦点となっています。2025年5月時点では詳細が確定しておらず、今後の税制改正プロセスで具体的な枠組みが明らかになる見込みです。
投資を検討する場合は、専門家のアドバイスを受け、自身のリスク許容度をしっかりと認識しておくことが望まれます。





コメント