令和7年(2025年)夏、相変わらずコロナニュースが流れています。今回は、「剃刀を飲んだようなのどの痛み」をキャッチフレーズとした変異株のニンバスだそうです。
COVID-19とmRNAワクチンは、2025年のパンデミックから早や5年、陰謀論と科学的根拠の間で揺れ動きながら、自治体や国によって対応が変わっていきました。
日本では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策としてmRNAワクチンが依然として主力として用いられています。しかし、アメリカではmRNAワクチンに対する政策が大きく転換し、開発資金の停止や州レベルでの禁止法案が相次いでいます。この動きは、日本国内のワクチン政策に波及する可能性があり、国民の間で「mRNAワクチンって、やっぱり陰謀だったんだ」という懸念の高まりを引き起こしています。
本記事では、アメリカの最新動向を概観し、日本との比較を通じて、mRNAワクチンの課題を探ります。
アメリカのmRNAワクチン政策転換:資金停止の背景

アメリカでは、COVID-19パンデミック時にmRNAワクチンが「救世主」として大々的に推進されました。ファイザーやモデルナ社のワクチンが迅速に開発され、数百万人の命を救ったと評価されている。しかし、2025年8月現在、連邦政府レベルでmRNAワクチン開発の段階的終了が発表されています。
米保健福祉省(HHS)は、生物医学先進研究開発局(BARDA)を通じて、約5億ドル(約740億円)に上る22件のmRNAワクチン開発プロジェクトの資金援助を停止する方針を明らかにしました。これには、鳥インフルエンザ(H5N1)などの次世代ワクチン開発も含まれます。
新たな保健長官に就任したロバート・F・ケネディ・ジュニア保険長官は、mRNAワクチンが上気道感染症(COVID-19やインフルエンザ)に対して予防効果が低いと主張。リスクが利益を上回る可能性や、公衆の信頼喪失を理由に挙げている。また、ワクチンがウイルスの変異を促進し、パンデミックを長引かせる恐れがあるとの見解も示しました。
一部の専門家は、この決定が将来のパンデミック対応を弱体化させる懸念が指摘されているが、ケネディ長官は従来の不活化ウイルス技術など、より安全で汎用性の高いプラットフォームへの予算シフトを強調しています。
この政策転換は、COVID-19ワクチン開発時の巨額投資(約180億ドル)と対照的です。BARDAは2006年の設立以来、感染症対策に多額の予算を投じてきましたが、mRNA技術の限界(変異対応の難しさ、効果の持続性不足、冷蔵保存の必要性)が露呈した形となりました。一方、がん治療などの非ワクチン用途でのmRNA研究は継続支援される見込みで、技術全体を放棄するわけではありません。
DNA汚染・金属粒子混入などを理由に州レベルで禁止運動が拡大:アイダホ州など

連邦レベルの動きに加え、州レベルではmRNAワクチンの投与自体を犯罪化する法案が複数提出されています。例えば、アイダホ州では共和党議員が主導する法案(HB 154およびSenate Bill 1036)が、mRNAワクチンの投与を軽犯罪とする内容で議論中です。理由として、DNA汚染、金属粒子混入、長期安全性の欠如、血栓や心臓問題などの副作用が挙げられます。アイダホ州はワクチン接種率が全米最低レベル(56%)で、COVID-19による死者数も5,000人を超えており、ワクチンへの疑念の高い州です。
ケンタッキー・モンタナ・アイオワ・テキサス・ノースカロライナ・ワシントンも
同様に、ケンタッキー州は2035年までmRNAワクチンを含む遺伝子療法製品の禁止を検討。モンタナ州では投与を軽犯罪化する法案(House Bill 371)が提案され、ワクチン接種後の癌増加や流産率上昇の証言が立法公聴会で共有されています。他の州(アイオワ、サウスカロライナ、テキサス、ワシントン)でも類似の動きがあり、一部郡では既にmRNAワクチン反対決議が可決されています。これらの法案は、mRNA技術の迅速開発が消費者保護規制を回避したと批判し、McCullough Foundationなどの団体が支援しています。
カナダも追随してグローバルな潮流に
これらの州法は、連邦の資金停止と連動し、mRNAワクチンの実用化をさらに制限する可能性が極めて高いといえます。国際的にも、カナダのアルバータ州、スロバキア、オーストラリアで禁止検討が進んでおり、もはやグローバルな潮流と言わざるを得ない状況です。
日本でのmRNAワクチン状況と懸念

一方の日本では、令和7年現在もmRNAワクチンがCOVID-19対策の中心です。ファイザー・モデルナ製ワクチンが主に使用され、変異株対応型も承認されています。日本のテレビや新聞ではあまり報道されませんが、アメリカの動きは確実に新たな懸念を投げかけています。
効果の限界
筆頭に挙げられるのが、効果の限界です。mRNAワクチンは変異株への対応が難しく、効果が時間とともに低下する点が指摘され、感染拡大への予防効果は極めて希薄でした。そのうちに、重症化予防効果だけが謳われるようになり、副作用(心筋炎など)の報告は増加の一途を辿りました。厚生労働省のデータですら、接種関連の健康被害が数千件に上っていますが、因果関係の証明が難しいということで保留状態です。
国際的に孤立する恐れ
このままでは、大東亜戦争のときと同じく、情報鎖国として国際的に孤立する可能性があります。アメリカの資金停止により、グローバルな供給 chain が乱れるのは明白です。接種率の高い日本はワクチン輸入に依存しているため、開発中止が新株対応ワクチンの遅れを招き、不安を助長する可能性が高いでしょう。
パンデミックによりすっかり免疫力の下がった日本人の、ワクチン依存とワクチンの不足する現実が、日本を未開発国と貶め、これまで当てにしてきたインバウンドからも見放される可能性があります。
日本独自の開発は不可能
さらに、経済・科学的な視点から、日本独自のワクチン開発が遅れている点が懸念されます。mRNA技術はがん治療などに応用可能ではありますが、アメリカの後退が日本の研究投資に悪影響を及ぼす可能性が出てきました。一部のメディアが米国の動きを報じているように、日本でも政策見直しの議論を活性化しなければなりません。
アメリカと日本の比較:いつまで続くのか?
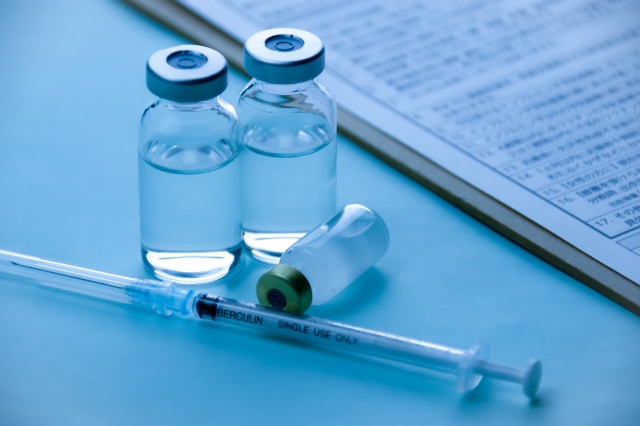
アメリカと日本を比較すると、アメリカは政治的・州主導の急激な転換が見られます。一方、日本は科学データに基づく慎重なアプローチを取っているが、国際依存度が高く、自己決定できない国となっています。
アメリカの資金停止が「mRNAワクチンの終わり」を示唆する一方で、日本では少なくとも2025年末まで現行ワクチンの使用が継続される見込みです。しかし、2026年以降は代替技術(不活化ワクチンや経鼻ワクチン)の導入が加速する可能性があります。
懸念されるのは、公衆衛生の格差拡大だ。日本がmRNAを継続すれば、国際的な孤立を招く確率が極めて高くなるでしょう。逆に、急な切り替えでワクチン不足が発生するリスクもないわけではありません。mRNAの利点(迅速開発)を活かし、安全性を強化した次世代技術の開発が急務です。
まとめ
令和日本のmRNAワクチン政策は、アメリカの動きを注視せざるを得ません。資金停止や禁止法案は、技術の限界とmRNAワクチンの信頼喪失に他なりません。
日本では科学的エビデンスと、堅実な実証データに基づくバランスの取れた対応が求められます。「いつまで続くのか?」の答えは、国際動向と国内データ次第ですが、国民の懸念を解消するため、政府は透明性の高い情報開示を急ぐべきでしょう。ただし、農水省のような拙速な備蓄米放出や溜池に水作戦は、世界の嘲笑の的となります。
慎重に、広い視野から、真に日本の未来を考えたうえでの、多様なワクチンを始めとしたあらゆる治療行為のプラットフォームの構築が求められます。





コメント