旧假名遣失落的日语“ゐ”的历史~“い”和“ひ”的区别及使用例保存版~
The History of the Lost Japanese Character “ゐ” in Old Kana Usage ~ A Comprehensive Guide to the Differences and Usage Examples of “い” and “ひ” ~
戦後の1946年(昭和21年)、GHQ主導による日本改革は、さまざまな面で日本の国力を低下させる狙いがあったと指摘されています。日本語の「現代かなづかい」への転換もその例に漏れなかったのかも知れません。
文化庁の発表した『現代かなづかい』によると「従来のかなづかいは、複雑であって、使用上の困難が大きい。これを現代語音に基づいて整理することは、教育上の負担を軽くし、国民の生活能率をあげ、文化水準を高める」としての日本語改革でした。
戦後、確かに生活能率は上がり、物は豊かになりました。しかし……「現代仮名遣い」の発表から80年になろうとしている2025年の7月2日、現役の総理大臣が「日本語は七面倒臭い」と発言するほど、憂慮すべき時代となっています。
トップが自国の言葉・文化を軽視し、蔑むような発言をするとは言語道断です。効率化・簡素化・単純化によって、本来あった大切なものを忘れつつあるのではないでしょうか?
本稿では、失われつつある「ゐ」の復興を目指して、その用途を詳しく解説します。
「い」と「ゐ」の違い
そもそも「ゐ」は、あいうえおのわ行において
わ・ゐ・う・ゑ・を
のイ段に用いられていた平仮名です。旧仮名遣い・歴史的仮名遣いとも呼びます。わ行は、基本的にWが入るため、下記のように発音します。
ゐ=wi
片仮名では、以下のように書きます。
ゐ=ヰ
現代では、和歌をたしなむ方の間で広く使われ、お笑い芸人の「よゐこ」、お酒の「ニッカウヰスキー」などで目にすることがあります。
「ゐ」の歴史
奈良時代(710~794年)
奈良時代には、「ゐ」は「wi」と発音され、「い」は「i」として区別されていました。 漢字音では、合拗音とよばれる「クヰ」「グヰ」という字音があり、それぞれ危「kwi」偽「g wi」と発音されていました。これは「キ」「ギ」の音とは区別されていました。
平安時代(794~12世紀末)
11世紀中期から後期頃の成立と考えられるいろは歌には、
いろはにほへと
ちりぬるを
わかよたれそ
つねならむ
うゐのおくやま
けふこえて
あさきゆめみし
ゑひもせす
とあり、あ行の「い」と「え」わ行の「ゐ」と「ゑ」は区別されています。
一方、寛智による『悉曇要集記』(1075年)には、以下のようにや行の「い」「え」、わ行の「わ」「を」が省かれています。
| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
| い | き | し | ち | に | ひ | み | り | ゐ | |
| う | く | す | つ | ぬ | ふ | む | ゆ | る | |
| お | こ | そ | と | の | ほ | も | よ | ろ | |
| え | け | せ | て | ね | へ | め | れ | ゑ |
このことから、平安時代の音韻は、わ行の「を」があ行の「お」と、や行の「い」「え」があ行の「い」「え」と同音となり区別を失っていたことがわかります。
ただし、『土左日記』(原本は承平5年〈935年〉頃成立)には、「海賊報いせむ」が「かいそくむくゐせむ」と混同する例もありました。
やがて、ハ行音がワ行に発音される現象(ハ行転呼)が散発的に見られ始め、語中・語尾のヒの発音が「hi」から「wi」 へと変化し、仮名における「ひ」と「ゐ」の使い分けが曖昧になっていきました。
鎌倉から室町時代頃まで(12世紀末~16世紀)
13世紀なかばに入ると「い」と「ゐ」はほぼ統合され、漢字音の「クヰ」「グヰ」もそれぞれ「ki」「gi」と発音されるようになり、「キ」「ギ」に合流しました。
南北朝時代に著された『仮名文字遣』(1363年以降成立)が和歌や連歌の世界で広く使われたが、それ以外の分野では「ゐ」と「い」および「ひ」の書き分けについての混用が多数見られます。
また、16世紀のキリシタン資料では、「い」と「ゐ」は 「i」 、「j」、「y」で記され、発音は同じだったことがわかります。
江戸時代
契沖(1640年 – 1701年)は、上代文献と呼ばれる『万葉集』や『日本書紀』が『仮名文字遣』(定家仮名遣)と異なることに気付きました。『和名類聚抄』(931年 – 938年頃成立)以前の文献では仮名遣いの誤用がまったく見られなかったからです。そこで『和字正濫鈔』(元禄8年〈1695年〉刊)を著し、上代文献に基づく仮名遣への回帰を主張します。
また、本居宣長は漢字音の仮名遣を研究し、『字音仮字用格』(安永5年〈1776年〉刊)で合拗音のうち「クヮ」「グヮ」のみを残し、「クヰ」「グヰ」「クヱ」「グヱ」はそれぞれ現実の発音に従って直音の「キ」「ギ」「ケ」「ゲ」に統合、新たに「スヰ」「ズヰ」「ツヰ」「ユヰ」「ルヰ」という字音を用いています。
明治以降
明治6年(1873年)には契沖の仮名遣を基礎に、古文献を基準とした歴史的仮名遣いが『小学教科書』に採用されました。また、字音については、本居宣長の『字音仮字用格』が基本となりました。
昭和以降
昭和21年(1946年)、大東亜戦争の敗戦後、GHQによる大改革が行われ、表音式の「現代仮名遣い」が公布されます。これにより、歴史的仮名遣いにおける「ゐ」は「い」に書き換えられ、使われなくなりました。
現代仮名遣いの制定以降、歴史的仮名遣いの見直しも進み、以下のような訂正が行われました。
- 「用ひる」は誤 ⇒ 「用ゐる」が正
- 「スヰ・ズヰ・ツヰ・ユヰ・ルヰ」は誤 ⇒ 「スイ・ズイ・ツイ・ユイ・ルイ」が正
英語国語化と戦後ローマ字化未遂
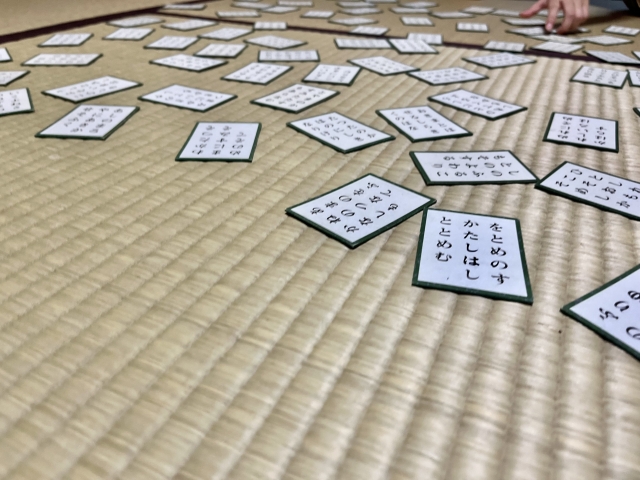
明治政府、第一次伊藤内閣で初代文部大臣となった森有礼は、1873年の『Education in Japan』の序文で「国語英語化論」を展開、その中で日本語の難しさをあげつらい、日本が国際的に競争力を高めるためには、英語を国語化した方がよいと述べています。
森有礼によれば、すでに英語圏の人種が世界を制しているため、まずは、彼らを模倣するしかなく、日本が対等の立場で独立を保つためには英語習得が必要だとのことです。
その真意はわかりませんが、散々な反発を買って実現には至りませんでした。そして、大東亜戦争の敗戦後、日本の弱体化に躍起になっていたGHQが日本語をローマ字表記にしようとしました。しかし、すでに日本人の識字率が高かったため、断念したといいます。
「ゐ」と「い」・「ひ」の使い分け
「ゐ」を使う語の中で、もっとも混同しやすいのが「いる」「ゐる」です。たとえば「ゐる」は「〜して居る(ゐる)・用ゐる・率ゐる・参る(まゐる)」に用いられ、それ以外はすべて「いる」を使っていました。また、紛らわしいのが「ひ」の使い方です。
以下の表は「ゐ」と「い」について紹介しています。それぞれの単語の頭に置かれる場合は「ゐ」もしくは「い」が用いられますが、以下表で紹介している場合を除いて、単語の中や下の場合は「ひ」を用いました。
| ゐ | い | |
| 動詞の使用例 | 居る(ゐる)膝行る(ゐざる)率ゐる用ゐる参る(まゐる) | 「老い・悔い・報い」などヤ行下二段活用(終止形が老ゆ・悔ゆ・報ゆ)の動詞は「い」を用います。「入る・要る・煎る」なども「い」 【音便】苛む(さいなむ)於いて聞いて咲いて就いて次いで |
| 名詞の使用例 | 猪・亥(ゐ)乾(いぬゐ)井草(ゐぐさ)井戸(ゐど)躄・膝行(ゐざり)田舎(ゐなか)家(ゐのこ)紫陽花(あぢさゐ)藍(あゐ)位(くらゐ)紅(くれなゐ)慈姑(くわゐ)潮騒(しほさゐ)起居(たちゐ)宿直(とのゐ)地震(なゐ)団居(まどゐ)基(もとゐ)鳥居(とりゐ)居丈高(ゐたけだか)敷居(しきゐ)芝居(しばゐ) | 熟寝(うまい)老(おい・おいらく)櫂(かい)悔(くい)小槌(さいづち)六日(むいか)報(むくい)幸(さいはひ)松明(たいまつ)一日(ついたち)刃(やいば)衝立(ついたて) |
| 形容詞 | 【音便】赤い青い嬉しい悲しい黒い白い楽しい近い遠い(とほい) | |
| 取り立て助詞 | ~ぐらゐ |




